記事
「日比野克彦館長による公開講評会」開催しました!(その1)
開幕最初の日曜日、日比野克彦館長の公開講評会を開催。150人の来場者が詰めかけ、作家と日比野館長のやりとりに耳を傾けました。
Art Award IN THE CUBE企画委員の日比野館長。AAICならではの企画、岐阜県美術館長であり、東京藝術大学学部長の日比野克彦が、「今日はバッサバッサと斬る(笑)」、“東京藝大特別講義”がはじまりました!

〈ニョッキ(如木)2017 〉 柴山 豊尚
ほのかに木の香りが漂う、積層材を積み上げ、グラインダーでかたちを削りだした空間。日比野館長は、「仕上げの部分で、もう少し精度があったらどうだったのかな、と思う。例えば、このとんがって曲がっている先の部分だけでも磨き上げ、工芸的に完成度が高かったら、だいぶ見え方が変わっていたのでは」と助言。「天井に伸びている柱のような部分、天井と隙間があるが…?」と問いかけると、柴山さんは、「(サイズを間違えて制作してしまったが)天井を突き抜けて伸びていると想像してもらいたい」と弁明しました。

〈Mimesis Insect Cube〉 森 貞人
「1500匹のガラクタ虫? 作っているところが見たいねえ」という日比野館長に、「昨日のOJUNさん中原浩大さんのクロストークで、“天井から吊った虫はなくてもいいのでは”と言われ、もう増やさないほうがいいと思って」と返す森さん。
日比野館長は、「どうしようもなく漏れ出しちゃう、虫が生まれる感じに任せて」と重ねます。森さんは、「いろいろ配置も考えて、最終的にこうなった」と、現在のキューブ状況で、自分の中では完成している感覚を説明。日比野館長は、それに対し、「森さんの場合、できたものがどこにどう飾られるかではない。作家には、得意分野と得意でないものがあり、自分の特徴がどこだと見極めるかどうか。森さんは、インスタレーションや空間構成は考えず、どんどん作り続けるのがよい」と、多くの作家や作品と接してきた見地から、方向性を助言しました。

〈移動する主体 (カタツムリ)〉 耳のないマウス
どこか非現実的な雰囲気を湛える、人間(形)が3体いるだけの空間。「〈ニョッキ〉とかは入った瞬間にわかるけれど、空間に滞留することでわかる作品がある。…あ、5cmくらい動いている…!人間が10cm動くのを、こんなに見つめることはない(笑)」と床に腰をおろした日比野館長。
「期待していることと違うことが始まるのに、人間は心惹かれる。観る人を裏切り、分かった気になっていたら、また裏切る。この作品は、1発目で(外から見えていた)壁にひっかかっている人、中に入って2発目が横たわった人、3発目が指先、4発目で動く。そうなってくると、鑑賞者は、“ない”ものまでみようとするんだ」
観る人の意識が想像する、“ない”もの―人間の内面に潜む世界を表出させる作品と示唆しました。

〈Missing matter〉宮原 嵩広
日比野「靴下を脱いで入るんだけど、このねっちょり感が…ね(笑)」 宮原「アスファルトは乾かない素材なんです」―という掛け合いから始まりました。

「彫刻家として、アスファルトという素材に着目したところが特徴。アスファルトはみんな知っているし、裸足で歩くことも知っているけれど、その組み合わせって、なんとなく想像はできても、体験するまで分からない。室内で、アスファルトの上を裸足で歩く経験は、ないよ」「そして、この空間の白と黒、アスファルトの持つ都会性や暴力性が感じられるよね」

アスファルトは、20世紀の美術において重要な素材であったけれども、今はそうではない。裸足で歩くことは太古から続く行為ですが、今はそうではない。そして、都会生活でありふれた自然物/人工物であるアスファルトの上を、室内で・裸足で歩く経験は、したことがない。物質をめぐる変異を体験する作品といえそうです。
〈Conduit(導管) 〉 三木 陽子
白い壁と黒いオブジェで構成されたモノトーンの空間。他のキューブから少し奥まった位置、そして落ち着いた照明があいまって、現実感と非現実感が絡み合う雰囲気を醸し出しています。

「直線がもっと多くて何箇所かだけが歪んでいるか、あるいは自由曲線が多くてどこかに直線が集まっているか。三木さんは、このような展示は他でもやっているけれど、この空間とのバランスにおいて、どちらかに寄る、落差がつけたらどうだったのか。もっと疎にしたり密にしたりね」「例えば、天井の照明レールは、『ここにあるものだ』と認識して、我々は自動的に意識からリセットし、作品とは思わない。天井の端とか床の隅とか、本来、管があるようなところにつけて、どこかがウニョっと曲がっているとか意識の反映をもっと演出しても良かったのでは」

技術的には充分な水準に達し、自身の個性を確立している作家への、作品の見せ方・演出の仕方に関わるアドバイスでした。「空間構成は考えずに作って」とした、森さんへのアドバイスとは、真逆と言えます。作家自身すら気づいていない可能性や、未開拓の部分を見抜く、教育者らしいメッセージでした。
〈HANDS〉 佐藤 雅晴
「手の所作がたくさんあって、蛇口から出ている水の温度を確かめている手、ピストルを撃つ手など、手だけをトレースした映像。人って、指でいろんな情報を集めているんだけれど、それをトレースしてバーチャルにし、実在しているものとのバランスが特徴」
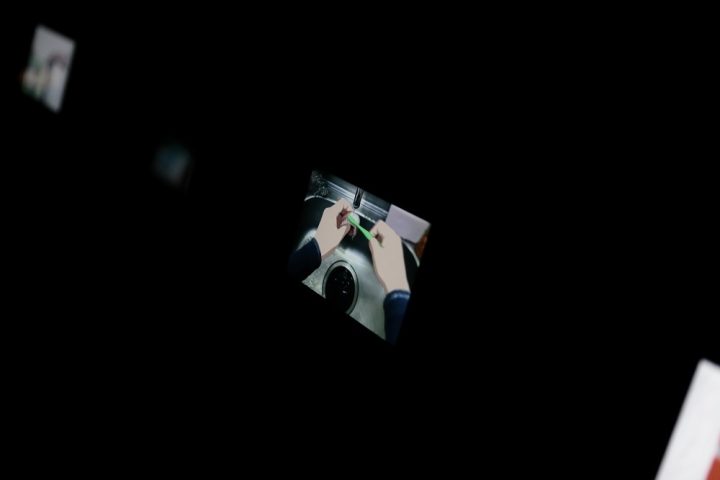
「空間としては、キューブをブラックボックスにして、小さなモニターが連続している見せ方。もっと大きな画面だったらどうだったんだろう、手を1分の1サイズで見せるやり方は、手に取る見せ方など、いろいろ想像の余地があると思いました」

次の作品の制作のため、佐藤さん本人は残念ながら不在でしたが、映像作品ならではの、見せ方に関わるヴァリエーションの可能性を感じました。
〈蘇生するユニコーン〉 平野 真美
「前の子犬の作品はリアルだったけれど、これはどこまでリアルを追求しようとしたのか、あるいはユニコーンだからフェイクでいいと思ったのか? 自分では何点くらいの出来?」と問う日比野館長に対し、「リアルさをとことん追求したかった。今の私の力では、いちばんいいものだと思うけれど、この作品はライフワークとして続けていくので、これからもっと到達していくと思う」と答えた平野さん。

「テーマパークは、入る人も『私を騙してください』と思って入っていく。キューブもそういうところがあって、騙してもらおうと思って入っていくんだけれど、リアルさの点で夢に誘いきれてないノイズ感、フォーカスが合わないところがある。それが次の課題だね」

日比野館長「犬の作品はその後どうなったの?」 平野さん「私のベッドの近くにあります。ときどき、メンテナンスで呼吸させています」という問答から、平野さんの作家人生における重要作品の、その後までが判明した館長トークでした。
平野さんは、後日の「公開手術(公開制作)」において、「館長にも『もっと完成度を』と言われたので…」と、質感・色・柔らかさがさらに本物に近づけた胃を作ってきて、ユニコーンの胃をとりかえたのでした。詳しくは、別途レポートします!

公開講評中、森さんのCUBEでは…、ガラクタムシを作っていました!

来訪者に開かれたこれからの美術館や展覧会、「作家の育成」というAAICの特徴を踏まえ、作家の次に繋がる助言がされた、館長の公開講評会でした。一方、作家も言いたいことはきちんと説明できており、来場者には新しい企画公募展の姿として共有してもらえたように感じました。芸術家が美術館にもたらす刺激や効果、岐阜におけるアートを巡る環境創造は、今後の取り組み次第なのだとも思われました。
残り8組の講評は、「その2」でご紹介します!
(Miyako.T)
