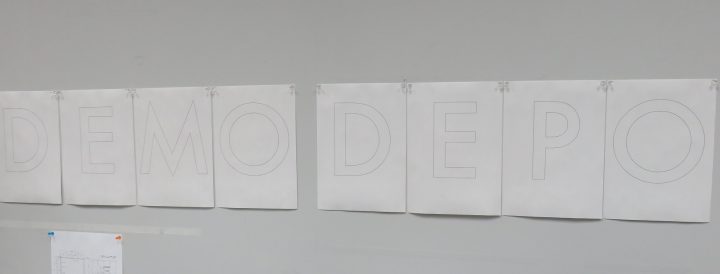水無瀬翔インタビュー「身体が向かう社会的な行く末、主体性の問題を提案します」
<DEMO DEPO>
デモ行為をロボットに代理させ、デモ行進までも商品として流通し得ることを批評的に表現します。実際に貸出可能なショップとして展示しますが、ロボットによるデモ行進の推進が目的ではありません。日常的に接する店舗を展示形式にすることにより、本来人間が身体を使用して行うはずの行為をロボットが代理するという、現実には可能な、ある意味滑稽な絵空事にリアリティを与えるのです。
―応募のきっかけを教えてください。
水無瀬:京都に近いコンペを検索していて、京都で説明会をされていたこと、岐阜に5年間住んでいたこともあって、応募しました。
―テーマ「身体のゆくえ」をどのように解釈しましたか。
水無瀬:「身体が向かう社会的な行く末」と解釈し主体性の問題を提案しました。現代社会では自身の思考や身体を使用せずとも、(直接または間接的な)代理によってあらゆる欲求が表面的には満たされるようになっています。
例えば、行動を起こさなくても誰かが色々なことを代行し、商品の購入から配送までワンクリックでできます。インターネットが(コミュニケーションや物流などの)伝送のあり方に大きな変更を加えたことが要因でしょう。欲求が表面的に満たされる感覚は、生きていくために必要な知恵や知識をデータとしてインプットする感じで、経験や学習結果のものではない。家(出発地)と学校(目的地)のあいだの通学路(中間)が消えて短絡してしまうような、道草できない感覚です。

―人間が主体的に行う行為の中から「デモ行進」を選んだ理由はなんですか。
水無瀬:人間の三大欲求(食欲・性欲・睡眠欲)、仮にその主体的行為の扱い方を決める法的ルールがあったら、それらを通じ主体と規範(秩序)の関係性について取り組みたかったのですが、現行の社会制度では許可制ではない。しかし、欲求をもう少し社会的に高次のレベルまで引き上げて考えると、意思や主張を社会に示すデモ行進が社会的欲求のアウトプットとして見えてきました。デモ行進を選択したのは、人間の主体的な活動の中で法制度化されているところが大きいです。
―「人間の主体的な活動の中で法的に制度化されているのがデモ」。デモに拘っている訳でないとしたら、デモでないモチーフを扱うことも考えていましたか?
水無瀬:考えていました。なぜデモというモチーフを選んだかは、過去作品のモチーフと共通する部分があります。モチーフ選びは、よく言えば柔軟に、素朴には偶然の出会いに頼っています。身体のおかれた場所や生活圏によって視点は限られると、実感することが多いからです。
実際に見たり聞いたり触れたものも、インターネットや文献を通して得られた知識もそう。全てにアクセスできている訳ではないしできるものでもない。特に作品制作で思考回路や価値観を再認識したとき、自分の立場が作品に反映されていると実感します。制作の上で全ての視点に開かれてないのはある意味欠点でもありますが、だからこそ重要な要素。(人間は)どれだけ客観的であっても、置かれた状況にかなり依存していると考えています。

―去年のデモが盛んに行われていた時期から作品構想が生まれたのでしょうか。
水無瀬:そうですね。東京に行ったときに新宿の歌舞伎町付近でヘイトスピーチのデモを初めて目の当たりにしました。内容はともかくビジュアル的に強烈で。デモ行進を順調に行うために警官や機動隊が配備され、さらにその周りには観衆がいて、普段目にしている光景からは想像できない状況だったのがとても印象に残っています。この体験から、どんなデモでも申請したら可能なのか、例えばロボットでもデモができるのだろうかという純粋な関心が出てきました。
―キューブと作品構想の関係についてお聞かせください。
水無瀬:いわゆるホワイトキューブが15点、2つの部屋に分かれて、美術館の中に設置される。一般的なホワイトキューブの状況とは異なります。その状況や空間でキューブがどう機能するのか、キューブを有効に使う一つの手段がお店だと思いました。
―行為をロボットに置き換えることのどういった部分に興味がおありですか?
水無瀬:ロボットやデモ行進を扱ってはいますが、社会批判の意図はなく、もっと別の次元に関心がある。また、社会におけるロボット化・自動化のあり方を主題としているわけではありません。
ある種の虚構を通じて人間がどう想像力を働かせるか、想像力の方向性に興味があります。
―アウトプットは、ロボットや映像だけど、実はコミュニケーション・身体性への興味が強い?
水無瀬:視覚表現以外では物語に関心があります。文学や哲学、人文系って普遍的なテーマとしてコミュニケーションに深い考察を与えていて、そうしたものに心がときめきます。
―作品の進捗状況を教えてください。取扱説明書もあったりする?
水無瀬:見せるコンテンツは、以前の作品を引き継いでいるのである程度決まってますが、お店の方向性はいくつか候補がある。応募当初は日常的なお店に近づけることを考えていましたが、色々な所に出掛けお店を観察する中でその必然性がないという結論に至りました。取扱説明書やその他書類は充実させていく予定。具体的なお店の内装に近づけるというよりは、機能の実現できる最小限の空間構成にしようと考えています。
―契約情報などは、来た人が自由に見れる?
水無瀬:日常でも、お客さんと店員で見れる情報が異なります。鑑賞者の方が、店員役・お客さん役・ロボット役を体験できるので、その空間の中でどういう役割として振る舞うかで閲覧できる情報が違うようにしようと思っています。
―面白そうな考えですね。
水無瀬:考えるのは楽しいです。10分の1スケールのマケットを作っていくと、アートの鑑賞・制作自体も子どものときのごっこ遊びの延長線上というか、要素は変形しつつも基本にあるんじゃないかなと感じます。
―店舗にするには、こういうのがいるよな、これもいるって思いを巡らせている?
水無瀬:できたらそのレベルから鑑賞者の方にも体験してもらえたら良いのですが。作品は最終的なアウトプットの状態になるので、そこまでは無理かも。現実にかなり近いけれど、全く別の想像力が働くような空間になって欲しいと思います。
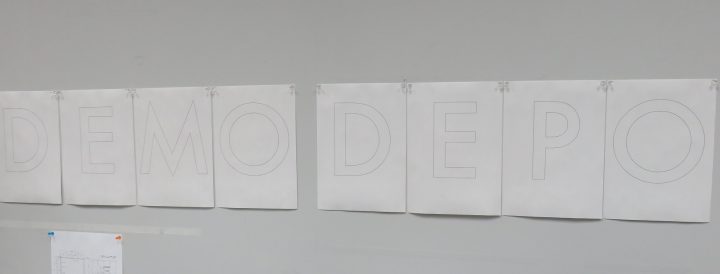
―水無瀬さんの作品で共通するテーマ、作る中で変化してきたものを教えてください。
水無瀬:共通するのは他者性。コミュニケーションのプロトコルが共通していないものに出会ったときに、アイデンティティが揺さぶられるような体験を与えてくれるものが僕の中での他者性。過去作品でも、一貫して他者がモチーフになっています。
デモ行進も、完全に他者的な出来事であったんですが、作品で扱っていくと、着実に以前とは違うようになってきています。
―創作活動において核となる部分があればお聞かせ下さい。
水無瀬:社会的な要素をモチーフとした今回の作品には、かつてうけた2つのワークショップが大きく影響してます。その一つが2015年に参加したポーランド人2人組によるワークショップ。パヴェウ・アルトハメルとアルトゥル・ジミェフスキという作家で、AAICの作品に使わる映像のコンテンツはそのワークショップの成果発表展で出したものです。今回の作品には確実に強い影響を及ぼしています。
もう一つが2012年に受けたフィオナ・レイビーという当時RCAのデザイン・インタラクション学科でクリティカル・デザインについて教えていた人が来日したときのワークショップ。彼女のある種アートというより、批評的デザインの観点からみた社会の捉え方もまた、今回の作品の構想を考える上で重要な要素になっています。
―過去作品についてご説明頂けますか。
水無瀬:〈I/F〉は動物と人間をモチーフとして扱い、奥にプロジェクションされた大きい画面と、手前に液晶ディスプレイを配置した、前後に距離のある映像インスタレーションです。動物の動きと人間の動きが同期している状態で、動物の動作が最初にあり、それを白塗りにした人間が真似するんですが、人間が訳の分からない動きをしている映像のシーンが始まって、だんだん明らかになっていくという構造。
動物と対話するにあたって、動物をまねて彼らが発信しているメッセージを理解する。鑑賞者も、パフォーマンスした人間が試みた、動物を擬人化しないコミュニケーションにアクセスできる。
文化的背景が少し違うだけで自分の発信する言語的メッセージやジェスチャーの意味合いが全く違うものになったり、伝わってると思ったことが違う文脈で捉えられたり、メッセージとして機能していなかったり、その逆もしかりですけど、そういう状況が当時は自分の中では強い問題意識として出てきていて。
動物園に行ったら、2匹のフクロウが凄く面白い動きをしていて、その光景に衝撃をうけたところから、なぜ自分が興味を惹かれたかを制作しながら理解していった。結果的にこの作品は何度も読み返す小説みたいで、かつての解釈と今では全く異なっていたり、自分の中では他人の作品のように重要な位置を占めている作品です。
その延長線上が〈gestures〉。〈I/F〉における人間の役割を監視カメラ型ロボットに置き換えて、〈I/F〉が人間と動物という関係性だとしたら〈gestures〉は動物と機械がテーマとなる作品ですね。扱っている内容的には一緒です。
―来年度、2018年3月、博士課程修了ですが、出品作と博士研究の関わりは。
水無瀬:間接的には関わっています。博士研究はもうちょっと幅広いテーマについて扱っていて。パヴェウとアルトゥルのワークショップの影響や、アートの文脈では扱いきれない要素、アートのあり方も含めて課題としてありますね。

―博士研究の仮タイトルを教えてください。
水無瀬:「道具箱としてのメディア・アート」。副題は「知・技術・権力の再分配と場の創造」ですね。副題に関しては指導教員の高橋悟先生の意図が強いですけど。
―指導教員の先生の意図はあるとは言いつつ、水無瀬さんの興味を―
水無瀬:興味を汲んでもらっています。言葉遣いは僕のとは違うんですが客観的な視点でみて頂いています。
―審査委員の中原浩大先生の興味の延長線上のまた新世代のような―?
水無瀬:社会的なモチーフをアートで扱おうとしているんですが、個人的な興味としては、人間の身体寄りの、どんな社会であれ人間が自覚するようなことができる身体性に関心があるので、そういう意味では鷲田清一さんや中原先生の価値観に共鳴するところがあります。
―では、最近面白かった、注目している作家は?
水無瀬:美術作品ではないんですけど、ミシェル・ウエルベックの小説。現代文学を最近読んでなかったんですが彼の視点が面白い。『地図と領土』は、今まで読んできた小説と比べると、人間の心理描写はほとんどありませんが、カメラや工業製品に関する詳細な描写が細かく、心理や人間性を強調するために機能していて、それがおもしろかったです。今扱ってる作品のモチーフの選び方とも似ている。自分の作品ではフクロウや人間など有機的な物であっても無機的に扱う癖があるのですが、表現方法を深めていく良いヒントになりました。
―岐阜県のIAMAS卒。IAMASでの経験はご自身や作品にどのように反映されていますか。
水無瀬:作家・水無瀬翔にはもの凄く大きい影響を与えています。学部は現在所属している京都市立芸術大学卒で、そこの修士課程に行かずに、IAMASへ。IAMASはメディアアートやデザインを含むいろんな表現や視点が存在し、それが分断されず広く関われる学校でした。美術的に評価されている価値観以外の価値基準、Fab、Makeなどのものづくり系の研究されている先生方も在籍されていて、いくつかプロジェクトにも携わらせていただいたのは重要な経験となっています。そうした環境で2年間過ごせた事がとても大きかったですね。
―岐阜に5年間いらしたという事ですが、IAMASは2年。残りの3年は…?
水無瀬:東海圏で就職を一時期して、プログラマーとしてスマホのアプリを開発する仕事に就いていました。家賃も安く、京都にはない部分が魅力的で、名残惜しいというか岐阜から離れられなかった。
京都は歩いて生活できるぶん密集し、一地方都市のなかでもコンテンツが集中していて自由な広大な感じがないです。
岐阜は土地がすごく広く感じられる。住んでいたのは大垣市で、最低でも自転車がないと生活しづらいですが、そのぶん窮屈さをあまり感じることなくのびのび過ごせる感じ。京都に住んでいた時とは生活スタイルが様変わりしました。伊吹山や木曽三川がほどよい距離感に存在して、大都市とも農村とも異なる街と自然の距離感が魅力的でした。岐阜全体について語れるわけではありませんが、岐阜はかなり好きです。
―来館者へのメッセージをお願いします。
水無瀬:受動的に鑑賞するインスタレーションとして見れるんですけど、店員として参加するのはもちろんのこと、ロボットになって参加もできる。ずっと店員として働くことも可能。役割に応じて、視点の違いや、提供されている情報の範囲が制限されていたり。制度的に作られている視点の制限、アクセスできる情報の違いも含めて、あらゆるレベルの視点の違いを楽しんでもらえたらなと思っています。
2016年11月12日 京都市立芸術大学にてインタビュー
聞き手:伊藤、鳥羽
作品制作の進行とともに、より作品コンセプトの純粋化に舵を切った水無瀬翔。映像からデザイン、デジタルなど幅広い分野を統合した、水無瀬独自の視点から創作しています。
(M.T)
作家紹介動画はこちら