一次審査講評
-

-
入江経一(建築家/デザインディレクター)
真実らしさを求めた遠近法から始まって、100年前には芸術という枠組みも壊され、今や情報は実体より大きい。そんな現在の世界に対して、「リアルのゆくえ」という問いかけに対する答えはあるのだろうか。その対象は身体でも環境でも情報でもいいが、燃えるような「リアル」と書き込まれた字があるのなら、答えなどいらないのかもしれない。私は次のような選考のガイドラインを決めた。
❶今の時代の状況を映し出すもの
❷新たな価値観を予見させるもの
❸社会や人々へのフィードバックがあるもの
いまだ語られていない言葉や言動を見せるような作品が見たいと、574点の作品に向かい合ったが、選ぶのはとても難しかった。アートの概念は強固なものだと実感する。逸脱や価値の定まらないものは審査で得票することも難しいが、ともかくも力作が選ばれた。実制作を通してさらに芳醇な作品となっていくのが楽しみである。
-
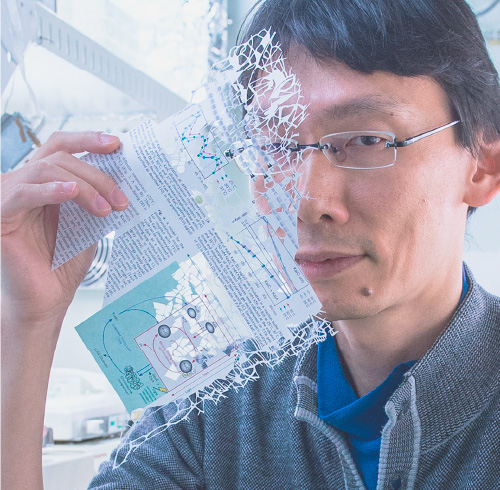
-
岩崎秀雄(アーティスト・研究者/早稲田大学理工学術院教授、metaPhorest代表)
様々なアイデアをキューブの形に実装する意欲的な企画が寄せられた。まずは応募してくださった作家の方々に心からお礼申し上げたい。私には様々な作品の可能性に出会える点で有難いことだったが、570あまりの作品からごく少数を選ぶのは、多くの作品を選外にせざるを得ないという点で苦渋に満ちた作業だった。私としては50点くらい残したいものがあった。全応募企画に対してそれぞれ短い覚書をしたためた上で臨んだ選考会議では、選考委員各自が真剣に臨んだが、投票が主体で、残念ながら十分な検討と熟議を経て入選作を決めたとは言い難い面があった。このため、一部の作品はその真価に気付くことのできないままに落選してしまったものがあると思う。これについては十分反省しつつ、今後の審査に心して臨みたい。また、野外展示や生物を含む展示など、意欲作ながら公募要領の規定を満たしていない点で採用できない作品が少なからずあったことは勿体なかった。とはいえ、選ばれた作品はどれも興味深く、どのように実装されるか早く見てみたいと思わせられるものばかりだ。キューブに実装される作品は、すべてリアルであり、リアルではない両義性として私たちの前に立ちはだかる。その一般的な前提を飛び越えて、刺さってくる体験を共有できる作品に出会えることを心待ちにしている。
-

-
北村明子(ダンサー・振付家/信州大学人文学部教授)
多くの制限と緊迫が続いた2年と少しの後、踊ることの“リアルのゆくえ”を考えることが当たり前になった身体で臨んだ一次審査。企画書、マケット、映像を行ったり来たりしながら、直感と思考の網の目が重なり合うような瞬間、脳内でイメージするキューブの中で、まだ存在しない作品と、ダイレクトに繋がるような時間を過ごした。身体感覚や自明の秩序が、ずれていったり、歪んだり、ひっくり返されたりするアイデアは、 “リアルのゆくえ”の可能性を無限に提示しながら時空を漂っているようだった。巡る思考が身体感覚へと表出し、それがまた思考へと戻されるといった循環運動を起こしているような、それは、ダンスと同じ現象のようにも思われた。直感を伴う体験で、身体感覚が変化する、思考、時空間、物質との接続。この体験はダンスの新たな感覚を切り開くことにもなるだろう。そして、実際の作品の存在は、それをどのように強化、または想像を超えたものへと飛躍してくれるのか、来年の4月への期待が大きく膨らむ。
-

-
四方幸子(キュレーター・批評家/美術評論家連盟会長)
「キューブ」への挑戦に加え、応募段階から新型コロナウイルス感染症の只中となった今回、そのような時代を反映した「リアル」とそのゆくえが、多くの企画から感じられた。応募者名も住所も性別も知らされない本公募ならではの審査は、内容から応募者を想像し始める興味深い体験でもあった。応募は、現代美術を中心に建築やメディアアートも多く、絵画、彫刻、工芸など美術全般に加え、このような枠組みでは困難に思えるパフォーマンスも目立った。内容には、清流や石、美濃和紙や美濃焼など、岐阜の豊かな自然や文化に関わるものも多く見られた。最も印象的だったのは、ポストパンデミックそして直面する国内外の諸問題を受け止めようとする切実さである。「リアル」へのアプローチは、知覚認識や身体性を扱うもの、過去を振り返ったり、人間中心主義を相対化するなど様々だが、いずれも人や社会、自然とのつながりを再接続しようとする意思が感じられた。とりわけ日常から記憶や死など視えにくいものに寄り添ったり、自然環境や生態系にミクロ、マクロな眼差しで関係を持とうとする企画を評価した。加えて、ユーモアやシュールさによって混迷を突き抜けようとする企画も評価した。
-

-
寺内曜子(美術家)
この公募展が他の公募展とは異なる1番の特徴は自立した大きなキューブという物体の存在だと私は思う。幅4.8 × 奥行き4.8 × 高さ3.6メートルの木製のキューブを自由に使えるという機会はなかなか得ることはできない。なので、自立したキューブ自体の存在を意識した作品企画かどうかを選考の基準とし、私個人の選択を行った。応募企画の多くは、キューブの内部空間に作品を「収める」ことを基本としたものに私には見えたが、規定の空間内に物や状況を収めるだけならば、何も自立したキューブがなくとも、美術館の室内で旧来通りの展示で済むのでは、と思われる。AAICの条件である、内部空間を持ったキューブを美術館展示室内に入れ子として展示するという二重構造は実は展示空間としては、とても難しいと私は思う。最終選考には残らなかったが、そのあたりを意識した企画も少数ながらあり、各々が独自の切り口で「キューブの実在」と取り組んでいて、興味深かった。一度ここまで応募条件を狭めても面白いのではと思った。
-

-
森村泰昌(美術家)
審査、苦手です。というのも芸術って元来、バトルとは対極にある領域だからです。芸術的価値を点数で推しはかるのは無理があるんです。作品同士を戦わせ勝敗を決めるなんていうのはむしろ邪道です。でも応募者全員を採用するわけにはいかないのですから、審査員としての私は何かを選ぶことになるわけで、だから「どうも苦手だな」とつぶやくことになってしまいます。
どうしようかと考えて、結局つぎの一点だけを頼りに選ばせていただきました。それは「これ見てみたい」という、一種の賭けみたいな判断基準です。応募された未来予想図を拝見して「これホントに実現できるのかな」とか、「ひとをバカにしたような提案だ」とか、そういう予測不可能性に遭遇すると、思わず「それ見てみたい」と前のめりになってしまいます。そこに賭けました。
なんども言います。芸術は優劣じゃない。ではなんだろうかと悩むのが芸術です。応募者全員のこの試行錯誤に、惜しみないエールを送りたいと思います。
-

-
山極壽一(総合地球環境学研究所所長)
アートとはそもそもリアルではない。それは言葉とは違うナラティブである。言葉が世界を切り分けて意味を与えるのに対し、アートは無意識の世界を揺らし、変質させる。二つの異なるナラティブがパラレルワールドを構成する。私たちはその間に浮かぶ。ただ、これまでのアートはリアルな世界とどこかでつながっていた。しかし、情報通信技術の進歩はその接続を外し、虚構の領域を拡大した。今回のテーマは現実とのつながりが曖昧になったアートをCUBEという小宇宙に解き放つ。それがどんな形となるのか。新しい技術は変革を重ねて古い技術を駆逐していくが、アートは原初の香りを常にどこかに漂わせている。その奥行きのどこかに人間がたどってきた足跡を感じ取ることができるのだ。その期待を込めて、今期の作品群を眺めてみると、リアルな世界に対する信頼が急速に薄れ始めていることがわかる。さて、そこから私たちは未来を感じ取ることができるだろうか。

