二次審査を終えて
二次審査講評
-

-
入江経一(建築家/デザインディレクター)
「触れるもの、絶対に触れないもの」
何組かの猿たちが梯子の上下で互いに見つめあっている。互いにそっくりだが片方の猿は片手がなかったり、のど首を欠いていたりして少しだけ完全とは言えない。猿の顔や胴体の一部は鉛のような表面で覆われていて、実は猿ではないことを暗示している。そう、一目見ればわかるように、このユーモラスな猿たちは今やたくさんの自己に分裂した「私」へのアイロニーなのだ。
一体自分はどこにいるのか。今ここにいる自分を自分だと思っているのは幻想に過ぎないのか。作者は分裂し複製された自己をアバターと呼んでいるが、いまやそれは一つどころか多くの自分となって現実空間にもネット空間にも拡散されてしまった。そんな私という存在に生じている事態を、この作品は諧謔をこめて突きつけているようだ。君が思っている自分(リアル)なんて不完全なものさ。猿は手ごわい。
-
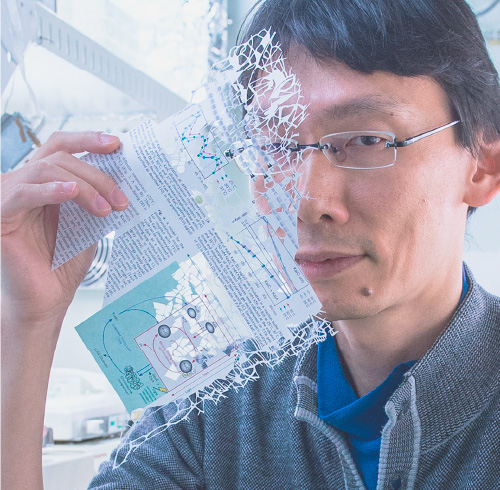
-
岩崎秀雄(アーティスト・研究者/早稲田大学理工学術院教授、metaPhorest代表)
大変な力作揃いで、まずは作者の方々、裏で奔走してくださった方々に心からお礼申し上げます。審査では、多様なアプローチと成果を前に、どこに力点を置いて評価するのか、テーマとの整合性をどの程度重視するのかなど多くの課題があり、紛糾とまではいかないまでも、様々な議論がありました。大賞作品の選出にあっても意見が相当割れました。河原の石を、集光された太陽光の熱で溶かし、地の下のマグマを想起させるプロジェクトについて、私は「今ココと壮大な地球史的時空間を詩的に切り結ぶ貴重な試み」と評価しました。
審査員賞に選ばせていただいた「橋」を巡る作品も、橋の狭義の機能から拡張し、抽象的なレベルまで含んで何かを繋ぎ、今ココと外部の関係性を開いていくポテンシャルの魅力と、地域に根差した地道なリサーチに惹かれました。ただ、どちらの作品も、本来持ちうる広がりや強度を十分に表現しきれていないのではないか、と僭越ながら感じてしまう部分もあり(私が見落としているだけかもしれません)、今後の発展・展開にも期待したいという意味で、推させていただきました。
他にも「サカサゴト」、「One room」といった作品にも、大いに惹かれるところがありました。鑑賞者の方々は、受賞作かどうかに気をとられず、ぜひそれぞれの作品に触れて、心行くまで体感していただきたいと思います。
-

-
北村明子(ダンサー・振付家/信州大学人文学部教授)
CUBE・・・制限とも自由とも捉えることのできるお題目に、全く異なるアプローチを持つ作品群は、一つや二つのテーマ性では収まらない多様性に満ちていた。実作品の体験は、困ったことにほとんど全てが楽しく、“Award”であることを忘れかけた程。視覚性、物質性から時空を広げて思考を巡らせ、五感からイマジネーションの解放・飛躍を誘発し、ストイックな強度やセンスの良さは、より深い解釈の旅を促進する。これらの魔力は作家・作品と鑑賞者の間に生じるものであり、漂う幽霊を追いかける行為のように、確信を失いそうになる波もやってくる。自問自答を繰り返し、“ブレない判断基準”の探求という、喜ばしくも苦しい試練の中で、時間経過とともに掴めてくるものがあった。それは、作家がテーマと真剣に向きあった証跡が、鑑賞・体験者に浸透し、ここから出発する“リアルのゆくえ”とは、いかなるものとして共有され、それが何と、どのように、どこまで繋がり得るものか、と、粘り強くも軽やかにも、問いかけ続けてくる、完結し得ない対話の力だった。
-

-
四方幸子(キュレーター・批評家/美術評論家連盟会長)
各作品のレベルは高く、しかも多様で、全体で見応えのある展覧会となっていた。審査では、キューブや今回のテーマへのアプローチ、ビジョンの実現性を重視したが、何よりも作品が放つ力やメッセージを受け止めた。各審査員の観点は示唆に富み、活発な議論が交わされた中、大賞については意見が分かれた。その結果選ばれた千葉麻十佳作品は、川で拾った石を太陽熱で溶かし「マグマに戻す」もので、溶ける石の映像や音の生々しさとともに岐阜から地球史や地球深部へと至る、ささやかながら鮮烈で壮大なまなざしによる。石から地球の連綿とした営みへ「リアル」を接続することで、想像力を喚起するとともに人間の立ち位置を問いかける側面を評価した。
審査員賞の北川純作品は、キューブを即物的に「箱」と見立て、コロナ禍の生活をモノの側から提示した。来場者が搬送物になる体験を提供することで、私たちはショッピングをしているようで実はさせられているのでは、と思わせるドライなユーモアが効いていた。
-

-
寺内曜子(美術家)
入選した14点は、個々の作品のアプローチや表現が違うので、ヴァラエティーの多さを楽しめる展覧会となっていると思う。その中から大賞を選ぶのはとても難しかった。審査員同士の正直な意見を交わして、丁寧に審査出来たのは良かったと思う。
私自身は各作家の「リアルのゆくえ」の内容を云々するよりも、①各作家が自分の信じる「リアル」を、言葉の助け無しに見ただけで伝わる説得力ある作品として完成させたか、②キューブを内側空間だけでなく外側空間もどう使っているか、を判断基準とした。
この基準②から外れた作品の中にも、完成度の高い作品は何点かある。キューブの制約を外すとより良くなっただろうと思われる作品もある。テーマを重視するかキューブを重視するかも作家及び審査員の意見の分かれるところだ。
私は今回の審査を終えて、この大きな自立するキューブから「必然的に生まれた」作品を見てみたい気持ちがより強くなった。
-

-
森村泰昌(美術家)
作品を作る。不思議な営みだ。我々はなぜこんなことをするのだろう。審査をしながらずっとそのことを考えていた。入選者14組の作り手たちは、みんな大変な苦労をしている。私もひとりの作り手なのでそれがわかる。だからみんなに賞をとってほしい。でもそれはできない。芸術の評価はスポーツのように数値で明確には表せない。輪郭線がぐにゃぐにゃ変わるおかしげなジグソーパズルのようで、そのとき次第でピタッと当てはまるピースの形がちがってくるらしい。芸術はたぶんAIにも予測が不可能な未知の領域なのだ。ざまあみやがれとちょっと勝ち誇った気分に審査員の私はなれたが、14組のみなさんには申し訳なく思う。ちょっとしたはずみで、誰が受賞するかがガラリと変わるからである。その予測出来ないスリリングな瞬間に審査員の私は立ち会えたが、それは神様の気まぐれで人の一生を左右するような不条理でもあっただろう。この不条理をかいくぐり、喜びにも落胆にも、まあこんなものだろうと鷹揚にかまえ、それでも自分はなぜこうして作品を作り続けているのかと問う。そういう芸術の仲間でいてほしい。審査員は出品者のジャッジメントではなく、むしろ共犯者であると思いたい。
-

-
山極壽一(総合地球環境学研究所所長)
入選した作品それぞれがとても個性的で評価をつけるのが難しかった。大きく自然に題材を求めたものと人間の内面に入り込んだものとに大別できるように思う。大賞の作品は、地球の表層に生きる私たちにその下を流れるマグマの有様を、岐阜の川の石から歴史を遡ることで示してくれた。
面白いと思ったのはJK in the street.で、リアルの行方の中心にいるのは実はJK(女子高生)ではないか。子供と大人の中間にいて「思春期スパート」のまっただ中にいる。心も身体も急速に成長する。変わっていく社会観、人間観の中で自分を見つめなければならない。本作品には、そんなリアルと反リアルのただ中で立ち止まり、もがいている姿がよく描かれている。「ふつうの」に込められた意味が二重に迫ってくる。「ふつう」を装いながら、その裏に隠れている願望が透けて見える。「違う」、「ウソばっかり」と叫びたくなる自分がいる。全編を流れる願いや現実を、あっさりとエピローグでひっくり返してしまうドンデン返しがすばらしい。作者の演劇的才能の高さがうかがえる。これを機会に大きく飛躍してほしいと思う。

